効果的な勉強方法
皆さまこんにちは!
優輝です。
まだまだ暑い日が続きますね。
新しいクーラーに変えてから、部屋は劇的に涼しくなりました。
今のクーラーってこんなにきくんですね!
逆に寒いくらいで、温度も29~30度に設定して靴下も履いています。
冷えすぎ―!!!
さて、今日は最近やっている勉強法について書きたいと思います。
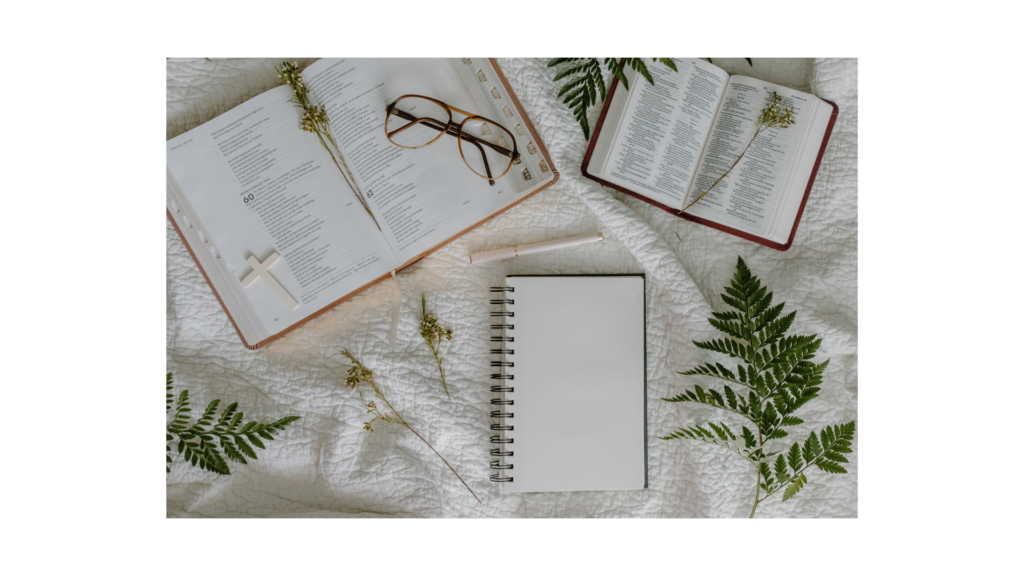
私は、勉強が大好きで、まあ、興味のあること限定ですが(苦笑)
次から次から湧いてくる興味のために、どんどんどんどんインプットを繰り返し続けてきました。今までは・・・
本を読んで、それをノートに書き写したり、動画講座を購入しては、ノートに書き写したり・・・
基本はノートに書くことで、インプットする!という方法をとってきました。
思い返してみれば、学生時代の勉強法も、試験前に必死に教科書を読んでノートに要点をまとめて・・・・みたいな事をやっていました。意外とこれが点数に繋がって、やったらやっただけ結果は出てたように思います。
ただ、上記の方法で集中して勉強することで、テストでは点数が取れても、、、割とすぐに内容を忘れてしまっていました。
いつも、後になって、あんなに勉強していい点とれたのに、時間がたったら学んだ知識が抜けちゃってるな~
と不思議に思っていた記憶があります。
今も勉強を続けている占星術に関しても、同じことが言えます。
あんなに書いて覚えたのに、あれ?なんだっけな?・・・と忘れてしまっていることも。
時間と共に忘れてしまうパターンと、ずーっと長期で覚えているパターンとの違いは何なんだろう???
それに対する「答え」のひとつの可能性が見つかりました!
それは、山口拓郎さんの書かれた書、「書かずに文章が上手くなるトレーニング」の中にありました。

脳には一時的に記憶を保存する「短期記憶」と、記憶の保存期間が長い「長期記憶」の二つの働きがあります。
「短期記憶」には一時保存された情報の内、脳が「これは覚えておくべき重要な情報だ」と判断した情報のみが、「長期記憶」へと移動するのです。一方、「長期記憶」に移動しなかった情報(短期記憶)は、その多くが、数時間~数か月で自然に消滅してしまいます。
「書かずに文章が上手くなるトレーニング」
私の学生時代のテストまでの短期間に必死に覚えた知識は、まさに「短期記憶」として、テストが終わったら役目を終えたとばかりに、じわじわと忘れ去られていたのでしょう。
占星術の勉強でも、同じように必死にノートに書いて、その時は「よし!知識が身についた!」と満たされていたけど、しばらくしたら、あれ?なんだっけ?とまた本を調べることになる・・という現象も、知識が「長期記憶」へと移動していなかったという事かもしれない。と思いました。
そして、ここからが、なぜ「短期記憶」から「長期記憶」へと移動しなかったのか?の部分です↓
もしかしたら、みなさんはもうお気づきかもしれませんが。
答えは「アウトプット」でした。
”情報の「理解→整理」を行う事によって、「短期記憶」の情報が「長期記憶」へと移動するのです。
事実、ふだんから人と良くおしゃべりをしたり、メモを取ったりしている人は、記憶から引き出せる情報量も多いはずです。
「話す」や「書く」を通じて、情報の「理解→整理」を行っているからです。””話すことも書くこともせずに、情報の「理解→整理」が行われることはないでしょう。
「書かずに文章が上手くなるトレーニング」
その結果、情報が「短期記憶」にとどまり、そのまま消滅してしまうのです。”
”「話す・書く→インプット→話す・書く→インプット→また話す・書く」
「書かずに文章が上手くなるトレーニング」
普段からこのサイクルを継続している人は、脳から引き出せる情報の量も多く、「長期記憶」の定着も、より強固になっているは素です。”
アウトプットとは、話す事、書くこと。
これをすることが長期記憶へ繋がる道だということです。
あれ?だとしたら、私ノートにめっちゃ書いてるから、それもアウトプットしてるってことだよね。
いやいや・・・それなのに、すぐに忘れてしまうのはなぜよ?
そう、ただ書けばいいだけではないみたいです。←これが私にとってめちゃめちゃ「目から鱗」だったところです!
”ちなみに、読書後に「原文丸写し」をすることは、アウトプットの効果としては微弱です。
「書かずに文章が上手くなるトレーニング」
「丸写し」の場合、前述した「情報を理解する→整理する」というプロセスを飛ばしてもできてしまうからです。
本の内容を書くときは、「丸写し」ではなく、一度頭で、「情報を理解→整理」したのちに、本を観ずに自分の言葉で書くようにしましょう。この方法であれば、「短期記憶」から「長期記憶」へと情報を移すことが出来ます。
この部分↑
まさに、私が勘違いして陥っていた罠の部分。
私は自分ではめっちゃ書いてるから=アウトプットしている「気」になっていたのです。
でも、実際には、情報の「理解」を得る前に、丸ごと覚える=丸暗記をしてしまっていた状態。
言うなれば、流れ作業のようなもの。
理解していないのに丸暗記・・・時間のないテスト直前などには有効かもしれませんが、本気で身に付けたい!今後もこの知識を役立てたい!使って行きたい!と思っている場合には期待できないでしょう。
この本を読んでから、私は、まずは理解をする。というステップに重きを置くようになりました。
そして、理解した後に、自分の言葉、自分の表現方法で、文章を書く、人に話す、などをするように心がけています。
ただ、この勉強法は、ただの「丸暗記」「丸写し」に比べて、時間がかかります。
理解するまで何度も読んだり、その後で、自分の意見を交え、言葉にしてノートやブログに表現することは、決して容易くはないです。
でも、確かに、「身についている」実感は以前と比べて格段に上がっています!!
もうひとつ、副産物として、色々なことに対して、ちゃんと自分の頭で「考える」という事が出来るようになっている気がします。
なんでも丸覚え、なんでも鵜呑みにする・・・・とは違う、自分なりに理解し、精査し、考え、発していくという行動は、他の誰かではない、自分自身を生きていく上でも重要なことなのだと、腑に落ちました。
長くなりました。
最後までお付き合いいただきありがとうございます!
感謝☆を込めて


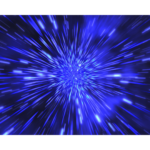




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません